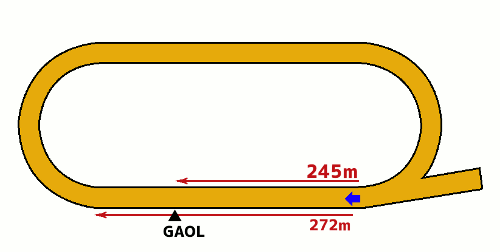水沢競馬場特徴と傾向
最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
水沢競馬場のコース特徴や人気傾向・枠順傾向・脚質傾向・騎手傾向・血統傾向など、馬券に役立つ水沢競馬必勝法を考案するべく、さまざまな角度から水沢競馬を攻略して行きたいと思います。
もくじ
詳細
- 水沢 850m 特徴と傾向
- 水沢 1300m 特徴と傾向
- 水沢 1400m 特徴と傾向
- 水沢 1600m 特徴と傾向
- 水沢 1800m 特徴と傾向
- 水沢 1900m 特徴と傾向
- 水沢 2000m 特徴と傾向
水沢競馬場の重賞一覧
コース特徴
水沢競馬場は岩手県競馬組合の主催する競馬場で、地方競馬では一般的な規模の競馬場です。公式資料によると、1周の距離が1200mで直線部がホームストレッチとバックストレッチで合計634mなので、コーナー部が566mと言う事になり、各コーナーの長さは141.5mで、サイズ感としては南関東の浦和競馬場をイメージすると近いものがあると思います。
水沢競馬の特徴は冬季になると降雪で常に馬場状態が不良の状態になりやすいのと、同じ岩手県競馬組合の主催する盛岡競馬場と違って高低差が全く無く、コーナー数も多くなりがちなので、盛岡競馬場で先行して最後バテてしまっているような馬が、水沢競馬場で活躍できるケースがあります。
所属馬のレベルはお世辞にも高いとは言えないし、騎手も他の地方競馬なら「こいつを買っていれば間違いない」と言えるような中心的な騎手がいたりするんですが、水沢競馬…と言うか、岩手県競馬にはそういう絶対的なジョッキーが不在です。
通常地方競馬は所属地域の騎手だけでレースを行いますから、各競馬場のリーディング1位の騎手は大体勝率20%を超える事が多いんですが、水沢競馬場ではリーディング1位の騎手の勝率が20%未満である事を見ても、ずば抜けた存在がいない事がわかります。
冬季は毎年開催が休止されるため、開幕からしばらくは殆どの馬が休み明けで出走する事になりますから、あまり馬の信頼度も高くありません。
単勝1番人気の勝率は40%を少し上回る程度で、これは園田や門別と同水準なので「地方競馬の中では平均的」な数値だと思いますが、上記のような人馬の信頼度から考えると、本命での一発大勝負よりは、むしろそういう馬を蹴って上手に本命馬の足元をすくえそうな穴馬を見つける作業が水沢競馬場の攻略法としては適しているように思います。
枠順・脚質傾向
水沢競馬場での枠順と脚質別の成績を見ていきましょう。
1枠の成績は(1着224回・2着249回・3着236回・着外1768回)で、勝率は9パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は28パーセントとなっています。
2枠の成績は(1着235回・2着244回・3着240回・着外1758回)で、勝率は9パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は29パーセントとなっています。
3枠の成績は(1着257回・2着266回・3着253回・着外1701回)で、勝率は10パーセント・連対率は21パーセント・複勝率は31パーセントとなっています。
4枠の成績は(1着234回・2着241回・3着286回・着外1716回)で、勝率は9パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は30パーセントとなっています。
5枠の成績は(1着283回・2着279回・3着281回・着外2033回)で、勝率は9パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は29パーセントとなっています。
6枠の成績は(1着327回・2着327回・3着312回・着外2406回)で、勝率は9パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は28パーセントとなっています。
7枠の成績は(1着402回・2着399回・3着406回・着外2849回)で、勝率は9パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は29パーセントとなっています。
8枠の成績は(1着460回・2着422回・3着405回・着外3078回)で、勝率は10パーセント・連対率は20パーセント・複勝率は29パーセントとなっています。
下の表は枠を考慮しない脚質成績
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 勝 率 | 30% | 12% | 3% | 2% |
| 連対率 | 48% | 26% | 9% | 5% |
| 複勝率 | 58% | 40% | 17% | 9% |
枠番別馬券数の履歴
| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 2025/12/14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 2025/12/15 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2025/12/16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 2025/12/21 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 2025/12/22 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 2025/12/23 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 2025/12/29 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 2025/12/30 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 2025/12/31 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 |
人気傾向
水沢競馬全体で各人気ごとの成績を調べてみると、以下のような結果になりました。(勝率は1着に来た割合・連対率は2着以内・複勝率は3着以内を表しています。)
水沢競馬場での人気別の成績を見ていきましょう。
1番人気の成績は(1着1068回・2着468回・3着271回・着外615回)で、勝率は44パーセント・連対率は63パーセント・複勝率74パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:85%・先行:76%・差し:54%・追込:41%となっております。
2番人気の成績は(1着490回・2着563回・3着369回・着外1001回)で、勝率は20パーセント・連対率は43パーセント・複勝率58パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:69%・先行:63%・差し:44%・追込:32%となっております。
3番人気の成績は(1着306回・2着401回・3着441回・着外1275回)で、勝率は12パーセント・連対率は29パーセント・複勝率47パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:64%・先行:50%・差し:35%・追込:26%となっております。
4番人気の成績は(1着210回・2着304回・3着360回・着外1547回)で、勝率は8パーセント・連対率は21パーセント・複勝率36パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:54%・先行:39%・差し:28%・追込:20%となっております。
5番人気の成績は(1着132回・2着222回・3着298回・着外1766回)で、勝率は5パーセント・連対率は14パーセント・複勝率26パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:41%・先行:30%・差し:20%・追込:16%となっております。
6番人気の成績は(1着86回・2着167回・3着209回・着外1937回)で、勝率は3パーセント・連対率は10パーセント・複勝率19パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:32%・先行:25%・差し:12%・追込:8%となっております。
7番人気の成績は(1着53回・2着123回・3着176回・着外2006回)で、勝率は2パーセント・連対率は7パーセント・複勝率14パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:32%・先行:19%・差し:11%・追込:8%となっております。
8番人気の成績は(1着36回・2着87回・3着136回・着外1962回)で、勝率は1パーセント・連対率は5パーセント・複勝率11パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:26%・先行:18%・差し:7%・追込:5%となっております。
騎手傾向
水沢競馬場での騎手成績を詳細に見ていきましょう。
山本聡騎手の成績は286-190-136-584で、1~4番人気での成績は274-171-115-333で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は12-19-21-251でした。
高松亮騎手の成績は244-202-159-996で、1~4番人気での成績は228-165-116-380で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は16-37-43-616でした。
山本政騎手の成績は236-215-205-964で、1~4番人気での成績は210-172-125-375で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は26-43-80-589でした。
村上忍騎手の成績は218-232-162-824で、1~4番人気での成績は208-196-129-411で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は10-36-33-413でした。
高橋悠騎手の成績は181-190-176-964で、1~4番人気での成績は158-149-111-310で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は23-41-65-654でした。
菅原辰騎手の成績は138-138-168-1274で、1~4番人気での成績は113-87-79-314で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は25-51-89-960でした。
塚本涼騎手の成績は118-117-135-1261で、1~4番人気での成績は93-77-67-258で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は25-40-68-1003でした。
坂口裕騎手の成績は116-110-147-664で、1~4番人気での成績は91-76-98-184で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は25-34-49-480でした。
鈴木祐騎手の成績は114-115-120-1105で、1~4番人気での成績は98-62-56-201で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は16-53-64-904でした。
岩本怜騎手の成績は110-128-150-1238で、1~4番人気での成績は92-87-98-311で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は18-41-52-927でした。
阿部英騎手の成績は98-101-111-976で、1~4番人気での成績は80-55-63-194で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は18-46-48-782でした。
小林凌騎手の成績は79-112-143-1087で、1~4番人気での成績は58-70-79-203で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は21-42-64-884でした。
陶文峰騎手の成績は74-68-62-378で、1~4番人気での成績は59-47-36-104で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は15-21-26-274でした。
大坪慎騎手の成績は73-95-88-958で、1~4番人気での成績は51-51-35-134で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は22-44-53-824でした。
佐々志騎手の成績は64-80-94-1023で、1~4番人気での成績は53-50-50-177で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は11-30-44-846でした。
関本玲騎手の成績は52-72-77-686で、1~4番人気での成績は37-48-38-114で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は15-24-39-572でした。
木村暁騎手の成績は46-54-48-303で、1~4番人気での成績は42-38-35-79で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は4-16-13-224でした。
南郷家騎手の成績は38-48-64-546で、1~4番人気での成績は27-33-35-80で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は11-15-29-466でした。
関本淳騎手の成績は33-42-50-393で、1~4番人気での成績は29-30-24-74で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は4-12-26-319でした。
坂井瑛騎手の成績は19-35-43-488で、1~4番人気での成績は14-16-16-61で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は5-19-27-427でした。
葛山晃騎手の成績は13-20-12-117で、1~4番人気での成績は8-12-7-27で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は5-8-5-90でした。
高野誠騎手の成績は10-14-7-95で、1~4番人気での成績は6-9-3-13で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は4-5-4-82でした。
石川倭騎手の成績は3-1-1-2で、1~4番人気での成績は3-1-1-2で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-0でした。
出水拓騎手の成績は3-2-2-9で、1~4番人気での成績は2-2-1-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は1-0-1-9でした。
桑村真騎手の成績は3-9-5-22で、1~4番人気での成績は1-9-4-7で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は2-0-1-15でした。
吉原寛騎手の成績は3-0-0-1で、1~4番人気での成績は3-0-0-1で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-0でした。
野畑凌騎手の成績は2-1-0-1で、1~4番人気での成績は2-1-0-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-1でした。
服部大騎手の成績は2-4-3-50で、1~4番人気での成績は2-0-1-7で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-4-2-43でした。
鷹見陸騎手の成績は2-1-2-2で、1~4番人気での成績は2-1-1-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-1-2でした。
他の騎手のデータも見るには【ここ】を押してね
笹川翼騎手の成績は2-0-0-3で、1~4番人気での成績は2-0-0-3で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-0でした。
金山昇騎手の成績は2-0-3-17で、1~4番人気での成績は2-0-2-3で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-1-14でした。
吉本隆騎手の成績は2-4-0-12で、1~4番人気での成績は1-3-0-1で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は1-1-0-11でした。
渡邊竜騎手の成績は1-0-0-1で、1~4番人気での成績は1-0-0-1で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-0でした。
西啓太騎手の成績は1-1-1-6で、1~4番人気での成績は0-1-1-3で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は1-0-0-3でした。
廣瀬航騎手の成績は0-0-1-0で、1~4番人気での成績は0-0-1-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-0でした。
和田譲騎手の成績は0-1-0-1で、1~4番人気での成績は0-1-0-1で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-0でした。
落合玄騎手の成績は0-1-0-5で、1~4番人気での成績は0-1-0-3で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-2でした。
木間龍騎手の成績は0-0-1-1で、1~4番人気での成績は0-0-0-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-1-1でした。
福原杏騎手の成績は0-0-0-1で、1~4番人気での成績は0-0-0-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-1でした。
服部茂騎手の成績は0-0-2-1で、1~4番人気での成績は0-0-2-1で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-0でした。
筒井勇騎手の成績は0-0-1-1で、1~4番人気での成績は0-0-1-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-1でした。
的場文騎手の成績は0-0-0-1で、1~4番人気での成績は0-0-0-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-1でした。
町田直騎手の成績は0-1-0-1で、1~4番人気での成績は0-1-0-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-1でした。
青海大騎手の成績は0-2-1-14で、1~4番人気での成績は0-0-0-2で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-2-1-12でした。
松井伸騎手の成績は0-1-0-1で、1~4番人気での成績は0-1-0-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-1でした。
小野楓騎手の成績は0-0-1-2で、1~4番人気での成績は0-0-0-1で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-1-1でした。
小松丈騎手の成績は0-1-2-25で、1~4番人気での成績は0-0-1-3で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-1-1-22でした。
山中悠騎手の成績は0-1-0-4で、1~4番人気での成績は0-0-0-2で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-1-0-2でした。
御神訓騎手の成績は0-0-1-0で、1~4番人気での成績は0-0-1-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-0でした。
宮川実騎手の成績は0-0-0-2で、1~4番人気での成績は0-0-0-1で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-1でした。
岩橋勇騎手の成績は0-0-1-3で、1~4番人気での成績は0-0-1-1で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-2でした。
岡部誠騎手の成績は0-0-0-1で、1~4番人気での成績は0-0-0-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-1でした。
阿部龍騎手の成績は0-1-0-0で、1~4番人気での成績は0-1-0-0で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-0でした。
クアト騎手の成績は0-1-0-2で、1~4番人気での成績は0-1-0-1で、5番人気以下の人気薄での騎乗成績は0-0-0-1でした。
血統傾向
どの種牡馬の産駒がどの程度馬券に絡んでいるのか、種牡馬ごとに馬券に絡んだ回数をカウントしたのが以下の表です。血統の系統別に馬名を色分けしています。
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| エスポワールシチー | 44 |
| トゥザワールド | 35 |
| アジアエクスプレス | 34 |
| ロージズインメイ | 33 |
| ビッグアーサー | 33 |
| ドレフォン | 33 |
| シニスターミニスター | 33 |
| エピファネイア | 33 |
| オルフェーヴル | 32 |
| ダイワメジャー | 30 |
| カレンブラックヒル | 30 |
| トビーズコーナー | 28 |
| ディスクリートキャット | 28 |
| サウスヴィグラス | 28 |
| ロゴタイプ | 27 |
| アイルハヴアナザー | 27 |
| ヘニーヒューズ | 26 |
| ビーチパトロール | 26 |
| リオンディーズ | 25 |
| ベルシャザール | 25 |
| ロードカナロア | 24 |
| アドマイヤムーン | 24 |
| ドゥラメンテ | 23 |
| ホッコータルマエ | 22 |
| フリオーソ | 22 |
| ディープブリランテ | 22 |
| ストロングリターン | 22 |
| イスラボニータ | 22 |
| メイショウボーラー | 21 |
| ベーカバド | 21 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。
関連記事
新着レース
- 根岸ステークス 過去10年データ傾向・予想
- 門司ステークス 過去10年データ傾向・予想
- 黒潮スプリンターズカップ 過去10年データ傾向・予想
- シルクロードステークス 過去10年データ傾向・予想
- 白富士ステークス 過去10年データ傾向・予想
- クロッカスステークス 過去10年データ傾向・予想
- 梅見月杯 過去10年データ傾向・予想
- 大井金盃競走 過去10年データ傾向・予想 【大井競馬場2600mコースの特徴】
- アメリカジョッキークラブカップ 過去10年データ傾向・予想
- 花吹雪賞 過去10年データ傾向・予想
- プロキオンステークス 過去10年データ傾向・予想
- 小倉牝馬ステークス 過去10年データ傾向・予想
- 睦月ステークス 過去10年データ傾向・予想
- 若駒ステークス 過去10年データ傾向・予想
- 兵庫クイーンセレクション 過去10年データ傾向・予想
- 報知グランプリカップ 過去10年データ傾向・予想
- 白銀争覇 過去10年データ傾向・予想
- ブルーバードカップ 過去10年データ傾向・予想
- 京成杯 過去10年データ傾向・予想
- ジャニュアリーステークス 過去10年データ傾向・予想